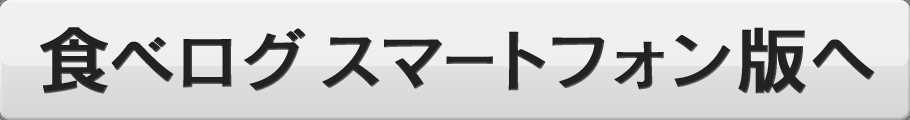箱根駅伝が好きだ。この15年程は、毎年1区から10区まで、ほぼ全てを見ている。一方で、この5年程は相反する複雑な思いも抱いている。
「箱根駅伝があることで日本は、マラソン等の長距離種目で、世界に差をつけられてしまっているのではないか」という思い。
箱根駅伝は学生スポーツの花形。東日本の大学の1競技会にすぎないはずなのに、陸上の大会としては、ありえないほど世間の耳目を集めるお化けコンテンツ。高校で活躍した選手は、まず箱根に出る権利のある東日本の大学を目指す。
有望な選手が10代から20代前半の貴重な時期を「箱根」に費やしていることが、陸上選手としての大成を阻み、世界との差を生んでいるのではないかとの疑念を拭えない。
箱根は5区、6区の山登り、山下りが勝負の行方を大きく左右する。山登りのスペシャリストで「山の神」と言われた柏原は箱根では大スターだったが、若くして引退した。彼は箱根の犠牲者だと思っている。
箱根のような完全にガラパゴス化した特殊なレースに注力することで、若い才能が空費されているのだ。
あくまで仮説の域を出ないが、元早大監督の渡辺康幸氏や大迫選手も実は似たような考え、問題意識を持っているのではないかと推測。
渡辺氏は箱根の大スター。SB入りし、同じく早大卒で箱根の大スターであった瀬古の指導を受けた。ケガに悩まされ、マラソンランナーとしては大成することなく、20代で引退。(マラソンの自己ベストは2時間12分台)
選手として引退後、ほどなく母校の駅伝の監督に就任。母校に箱根優勝の栄誉をもたらすも、10年余で監督を退任。(ちなみに大迫選手は早大時代、渡辺監督の指導を受けている。)
この渡辺監督の退任、大迫選手が大学横断的な強化の枠組みを作ろうとしている動きから、私は上記の仮説を立てている。
40年~50年前なら、「箱根に向けて走力を鍛えること=長距離選手としての成長」だったのかもしれない。
瀬古はその最高の成功例。彼は箱根での活躍を経て、社会人ではSBに所属。マラソンで2時間8分台の自己ベストを持ち、1980年代前半は世界最強のマラソンランナーの一人だった。ラストスパートでイカンガーを置き去りにして勝利する等、レース終盤のラストスパートに定評があった。
そして、この瀬古の「成功体験」から、日本の大学の陸上界は長く脱却できず、箱根をメインにした、選手の発掘、育成をしてきた気がする。
(完全に脱線するが、瀬古の最大のライバルはダイエー所属の中山竹通。長い手足をいかした迫力あるフォームが目に焼き付いている。圧倒的な走力で前半から抜け出す先行逃げ切りスタイル。個人的には歴史上、男子マラソンで最も金メダルに近かったオリンピアンだと思っている。ただ1988年のソウルでは4位。ソウルでは、いつもの先行逃げ切りではなく、集団の中でのレース運び。結局、抜け出すことができないまま終わった。ソウルは酷暑だったことが、慎重なレース運びをさせたのかもしれない。確かソウルの優勝タイムは2時間11分台。中山のベストタイムも2時間8分台だったので、勝機は十分あったはず。自分らしからぬレース運びで勝てなかったことが、よほど悔しかったのだろうか「4位ならば、ビリでも同じ」との発言をして、世の中の顰蹙を買ってしまった。エリートの瀬古とは犬猿の仲。指導者になってはいるものの、中山は表舞台からは姿を消している。中山以降、私自身は今回も含め、オリンピックの男子マラソンを期待を持ってみたことは1度もない。)
脱線したが、現在のマラソンは高速化。1980年代なら2時間8分台が一流選手の目安だったが、今のキプチョゲの世界記録は2時間1分台。(非公式では2時間切りの1時間59分という記録まで出している)
キプチョゲは1万mからの転向。日本がもし今後本気でオリンピックのマラソンでのメダルを目指すのなら、箱根をメインに据えた選手の発掘、育成から一刻も早く脱却し、若いうちから徹底的に1万mの走力を鍛え、高地で心肺能力を鍛える。そういう意識を持たなければ、世界との差は開く一方だろう。
大迫が単身ケニアに行き、大学を超えた選手の交流、育成をしようとしているのも、そうした危機感の表れだと思う。
ちなみに今回のオリンピックの1万mの代表は相澤選手(※)東洋大学4年生の時に2区で区間新記録を作った箱根のスター。その彼は今回の1万mで17位に終わり、世界との差を口にした。そのことが極めて象徴的。
(※)福島県須賀川市出身。1964年の東京オリンピック銅メダリスト円谷(つむらや)幸吉氏と同郷。幼い頃から、円谷氏の名を冠するクラブやレースで活躍。蛇足だがNHKは相澤選手を紹介する特集の中で、円谷氏を「つぶらや」と誤った読み方で放送していたので、怒りを禁じえない。